2021年9月9日
購買実務で成果を積み重ねてきたスミダ電機が、CPP資格の導入によって購買力をどのように客観化し、組織と人材の成長につなげたのか。その変化と手応えについて、同社の坪井氏に伺った。また、現在CPP-B級取得に向け学習中の岩見氏・小森氏にも同席いただき、三者それぞれの視点から資格取得の意義をお聞きしました。
坪井様 岩見様 小森様
※以降敬称略、所属・役職はインタビュー当時
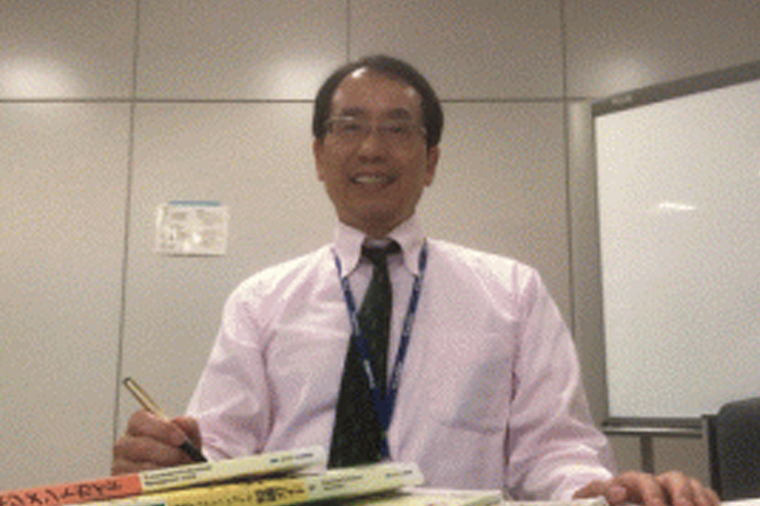
御社の組織体制と、ご自身の担当業務について教えてください。
坪井
スミダ電機は宮城県名取市に本社を構え、アジアでは中国に7拠点、ベトナムに2拠点、さらにタイや日本にも生産拠点を展開しています。各工場には購買部が設置されており、アジア購買本部は中国・広東省に位置しています。私は現在、このアジア購買と日本の技術購買の両方を担当しています。
日本では、主に開発段階における購買業務を担い、各部門と連携しながら最適な部材の調達を図っています。さらに、量産購買や日々発生するトラブル対応など、多岐にわたる業務にも対応しています。開発購買の現場では、製品開発の初期段階から関わり、事業部と連携して新製品の立ち上げを支援している状況です。
技術購買部には岩見と小森も在籍しており、製品開発の初期段階から関わっています。両名は、開発部門や設計担当者と連携しながら、必要な部材の選定や調達の提案を担い、現場に密着した購買活動を通じて、開発上の課題解決にも大きく貢献しています。

CPP資格の導入を検討された背景について教えてください。
坪井
以前からVEやVAによるコスト削減、部材の共用化などには積極的に取り組んでおり、自社の購買力には自信がありました。しかし、全社的な業務見直しの際、トップから「当社の購買部門はプロフェッショナルですか?」という問いを投げかけられたのです。そのとき、「当然プロフェッショナルです」と即答したものの、それは社内基準における評価であって、他社と比較できるものではないと気づかされました。そこで、購買に関する客観的な資格制度を探していた中で出会ったのがCPPでした。
また当時は、業務の進め方が担当者ごとに異なり、属人化が進んでいた点も課題でした。ノウハウや判断基準が個人に依存しがちで、組織全体としての共通項が不足していたのです。そのため、新人や若手が実務を通じて学びにくく、育成の進度にもばらつきが生じていました。そうした状況を踏まえ、CPPを導入することで知識の体系化と標準化を推進し、人材育成と組織力の底上げを図ろうと考えました。

資格取得の取り組みは、どのようにスタートしたのでしょうか?
坪井
最初にCPPのガイドを数冊購入し、社内で読み合わせや勉強会を始めました。しかしコロナ禍で集合学習が難しくなり、試験バウチャーを活用して個別に受験する形に切り替えました。実務に自信があるメンバーを受験させたのですが、結果は全員不合格。内容は理解しているはずなのに、思うように点が取れませんでした。このギャップに直面したことで、ガイドの内容を体系的に学ぶ必要があると痛感しました。
そこから見えてきたのは、実務に頼った属人的な判断の限界です。経験が豊富なベテランであっても、理論的な裏付けや定義に基づく対応が必要な場面では差が出ることが分かりました。この経験を通じて、組織全体として知識を標準化し、再現性のある購買スキルを身につける必要性を実感しました。

オンラインセミナーの導入について教えてください。
坪井
CPPのガイドは非常に内容が豊富で、分量も多く、独学では要点をつかむのが難しいと感じていました。そこで、CPP協会から届いたオンラインセミナーの案内に注目しました。サンプル動画を視聴したところ、文章主体のガイドとは異なり、図表で全体像を示しながら要点を丁寧に説明してくれる構成になっており、非常に理解しやすいと感じました。
受講者の負担も軽減されると判断し、まずは私が試験対策として導入しました。会社からは就業時間内の学習も許可されていたのですが、実際には購買業務の特性上、突発対応も多く、まとまった時間を取るのが難しいため、自宅での学習を中心に進めました。特に便利だったのが倍速再生機能です。講義の進行を1.5倍速、2倍速と自分のペースで調整できたことで、時間を有効に使いながら理解を深めることができました。結果として、当初より早いタイミングで受験準備を整えることができ、非常に効率的に学習を進められたと感じています。
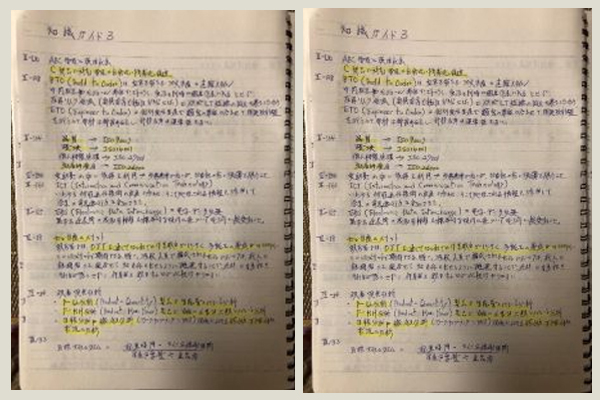
受験を通じて、ご自身や組織にどのような変化がありましたか?
坪井
体系的に知識を整理できたことで、自分の業務に対する理解が深まりました。これまで経験則で進めていた判断が、CPPの理論と結びついたことで「なぜそれをするのか」という確信が持てるようになりました。さらに、CPPを取得したメンバーの中には、自信をもって提案や交渉に臨めるようになった社員も増えています。用語や考え方を共通化できることで、開発部門など他部署との連携がスムーズになったという声もありました。
部門全体としては、育成や評価の基準が明確になったことで若手社員の成長速度が上がり、チームの底上げにもつながっていると感じています。
CPPの魅力は、単なる知識習得にとどまらず、実務にどう応用するかという思考の枠組みを身につけられる点にあります。理論や用語を学びながら、それをどのように現場に落とし込むかを体系的に理解できるため、日々の業務の中で判断や提案に自信を持って臨めるようになります。今後は、中国や東南アジアの拠点にもこの教育体系を展開し、グローバルに通用する調達スキルと組織基盤を強化していきたいと考えています。
岩見ガイドを繰り返し読み込む中で、理解が深まる実感があります。前回の受験では見落としていた点にも気づくようになり、学ぶべきポイントが明確になっています。
小森 現在は子育てと両立しながらの勉強ですが、少しずつ自分のペースで進めています。周囲にCPP取得者がいることでモチベーションも高まり、今後の成長につなげていきたいです。
