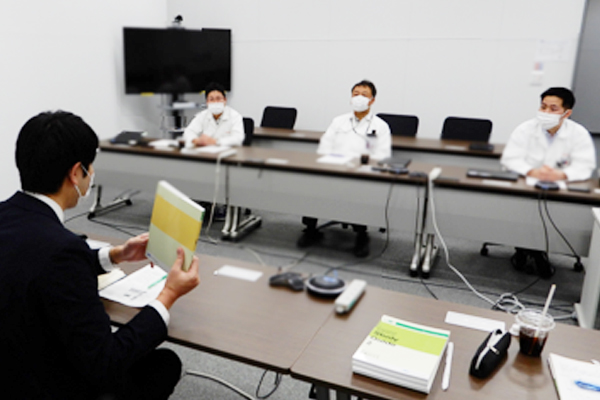2021年6月10日
株式会社ホンダアクセス 購買部 品目ブロックの方々へ、CPP資格制度の導入やご活用について事務局がお伺いしました。
購買部 品目ブロック
ブロックリーダー 主幹 原口 裕孝 様
主任 西松 直也 様
チーフ 繁田 啓輔 様
※以降敬称略、所属・役職はインタビュー当時

まず、現在のお立場、役割について原口さん、西松さん、繁田さんの順番で教えていただけますでしょうか?
原口
弊社はHonda四輪車の純正アクセサリー(用品)を取り扱っている会社です。
純正アクセサリー開発は親会社であるHondaの開発部門と連携して行われており、私の属する購買部 品目ブロックは、実務として車両本体の開発と連動しながら純正アクセサリーの部品の購入を担う部門となります。
私は、その品目ブロックで、ブロックリーダー、一般的に言うと課長職を担っております。
西松
品目ブロックの中には、純正アクセサリーの部品を主に、内外装品と電装品を担当するグループがそれぞれありますが、私はその中で内外装品のグループのグループリーダーを担っており、一般で言う係長職を担当しております。
弊社は非常に多岐にわたる部品を多くのお取引先から購入させていただくのですが、基本的な実務としましては、どのお取引先で生産いただくのか、いくらで購入させていただくのか、といった選定、交渉、初回納品までの調整などを行っています。
繁田 私は西松のグループで内外装品目の購買を担当しており、合わせてグループリーダーの西松の補佐をしております。
現在、ホンダアクセス様では何名くらい資格取得をされていらっしゃるのでしょうか?
原口 CPP-A級が2名で、CPP-B級が3名ですね。
西松 私と繁田がCPP-A級を取得している2名でして、若手層を中心に受検している感じですね。
原口 この資格を導入し始めたのが2~3年前からだよね?
西松 そうですね、たしか2019年の年初めくらいからですかね。
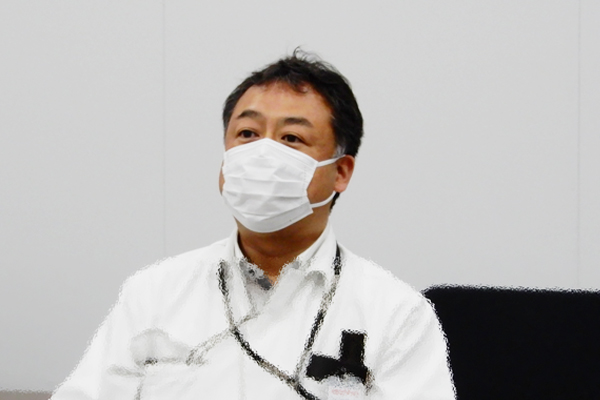
ホンダアクセス様で導入されたきっかけについて教えていただけますでしょうか?
原口
2015年頃までは引退前の先輩ベテラン社員に若手育成をお願いして若手勉強会を行っていました。2016年頃から、別の先輩社員に若手育成を新たにお願いした所、その方がCPPを見つけてきて「一度、試験的にやってみよう」ということになりました。
人材育成・若手育成では、それまで先輩社員からの教育や、若手同士が気づき等を共有しながら勉強会を行っていたのですが、専門的・教科書的なCPPを実際に見て、我々があまり知りえない情報や、深い情報が含まれていることが分かり、また資格試験もありましたので、「じゃあ、試験にチャレンジすることを含めてやってみようか」ということで始まりました。
先程CPPをグループに紹介された先輩ベテラン社員の方は、購買調達の業務経験年数としてはどのくらいだったのでしょうか?
原口
弊社では希望すれば最長65歳まで働くことができます。前述のCPP導入を提案した先輩ベテラン社員は60歳を過ぎた方で、購買調達の業務経験はありませんでした。元々は管理部門の方で、その後こちらに異動してきました。
当初、若手育成をお願いしたものの、どのように教育をしようかと考えられた結果、CPPにたどり着いたのかなと思います。
当時は、購買調達を長年やってきたメンバーがあまりいなく、今のように若手教育とか人材育成ができるメンバーが正直どのくらい在籍していたか分かりませんでした。皆で考え、独自のマニュアル等を作成しながら対応していたものの、CPPのような教科書的なものは全く無く、手探りで行っていました。
実際に調達プロフェッショナルスタディーガイドの購入や、メンバーへ展開するにあたって何か障壁になったことなどありましたでしょうか?
皆様 特になかったですね。
原口
ただ思い返すと、若手社員が積極的に借りに来ていたような印象がありますね。調達プロフェッショナルスタディーガイドを若手社員に見せると「面白そうだから、借りて良いですか?」といった反応が返ってきて、徐々に借りていく人も多くなっていきましたね。それに伴って、数冊ずつ追加発注していき、今は5セット程あります。
また、弊社は台湾に現地法人があるのですが、「購買業務をどのように連携するか?」という課題感もあり英語版も購入しました。
多分、そんなに勉強に対しての抵抗感というのはほとんど無かったのではないかと思いますね。
繁田 そうですね、どちらかと言うとボトムアップで、「やらされている」というよりかは「やりたくてやっている」という感じでやっていたような雰囲気でしたね。
原口 私のスタンスは、調達プロフェッショナルスタディーガイドを「読むように」「受験するように」といった指示を出した覚えは無くて、メンバーの皆さんが「読みたいです」「受験してみたいです」といった自発的にやられていた印象ですね。

少し 調達プロフェッショナルスタディーガイドの中身について教えていただきたいのですが、役に立ったという内容、テーマがあれば教えてください。
西松
私が印象的だったのは、お取引先との関係構築や、選定の部分ですかね。今までは独自の考えで構築してしまっていましたが、相手先のQCDDの実力度や協力度などが体系的に書かれていて、今まで自分達でやってきたことと同じ部分もあれば、まだ把握してなかった部分もあり参考になりました。
あとは「言葉(専門用語)」ですね、メンバーで話していても「あれ、この言葉で合っているかな?」や、「確かにこういう言葉だと通じる、分かり易い」という場面もありました。
原口
先程、西松がQCDDを例に挙がりましたが、業務で点数化しやすい部分は管理しやすいですね。
ただ購買の中で、見積もりなどは数字で表されますが、協力度合いなどを数値化することには課題感を持っています。
我々の調達品目でも少ない数を購買している部品もあり、その点では、お取引先に無理をいってお願いして作ってもらうこともあります。お取引先が我々と「どう向き合って、協力していただいているのかな?」という観点と測り方などを調達プロフェッショナルスタディーガイドで学びましたね。
試験対策以外でも、普段から調達プロフェッショナルスタディーガイドを読み返す機会はありますでしょうか?
繁田
読み返しますね。誰でも見られるように分かり易い場所にいつも置いてあって、私も言葉の意味や表現があっているのか確認します。あとは、サプライヤー戦略を立てたりする際の確認であったり、社内外でどのように説明すれば分かり易いか等であったり、色々な場面で再確認しています。
最初は凄いボリュームのあるテキストなので大変だな、と思っていたのですが(笑)、一通り見終わったあとも、不思議とまた見ていて、そうして気づいたら何回も見るようになって、今では抵抗感は全くないですね。
西松 何か業務で困ったときとか、「確かこれって、調達プロフェッショナルスタディーガイドのあの辺りに書かれていたよね?」みたいな会話があるよね(笑)?
繁田 そうですね(笑)。
調達プロフェッショナルスタディーガイドを導入される以前と比べて、社員の方の業務レベルや質がレベルアップしたといった実感がありましたら教えてください。
原口
レベルは上がっていると思いますね。弊社は開発系の会社なので、開発フェーズごとに内部報告会がありまして、その報告内容のレベルが凄く上がったな、と思いました。
当然ながら、レベル差は多少ありますが、若い社員もコスト検証やML(Maker Layout)選定の視点、根拠を説明できるようになりましたし、私も相手の意図や伝えようとすることが分かるようになりました。
極端に言うと、コストの安さだけでしか判断できなかった部分が、QCDDの観点やコスト検証がきちんとなされるようになりました。
西松 プロジェクトの背景や必要性に応じて、「今回コストが高くても、品質を守らないといけないよね」といった場面でも、定量的かつフェアな評価を、社内で提案できるようになりましたね。

サプライヤーの皆様とのやりとりの中で変化などありましたでしょうか?
繁田 そうですね、新しいお取引先とやり取りさせていただく際には、「CPPのような共通言語があると伝わりやすいかな」という感覚はあります。
これからの組織目標に対して、CPPの活用などが含まれていたらご紹介いただければと思うのですが、いかがでしょうか?
原口
弊社、購買と調達は分かれており、日程管理とコスト・MLなどは分担していますが、日程管理など一部の業務は我々のグループで取り込んでいくことをやり始めています。本当の意味での購買調達という観点で、購買調達の一連の流れと業務を一貫してみることができる人材を育成していければと思って、取り組み始めたところです。
私も、経験したことのない領域での業務ですが、人材育成には終わりは無いと思っているので、CPPのような教科書を参考にしながら、“真の購買部門を目指していきたい”ですね。
弊社内で“信頼される購買部門として役立ちたいな”っていう思いがありまして、先ほど申しましたが色々な部門と一緒に仕事をする中で、「分からないことは購買に頼ろう」「購買がいると助かるよね」と思われるようになりたいと思っています。
やはり、そのように思ってもらうためには、色々業務経験を積む中で、CPPの勉強しながら、メンバーの皆さんと一緒になって向かっていけたらと思っています。
西松 私は、マネジメントと現場の間のポジションにいますが、マネジメントの方針を現場に浸透させたり、逆に現場からの意見を吸い上げてマネジメントに提案したりしていく中で、「CPPを活かして何をしていこうか」ということや、「自分の経験をプラスアルファして、次の世代に何を伝えていくか、残してくか」などを考えています。
繁田
私は、世の中に役に立つということを「購買部門という立場からどのように貢献していくか?」ということや「購買部門として付加価値とは?」ということの追究ですかね。
そういったところに、CPPを活かしていきたいなと思っていますね。
お客様とダイレクトに接すると、そういった場面で得られる感謝や感想などはやりがい、達成感に繋がると思うのですが、我々はお客様と直接的に接する機会が少ないので、そこに自分の仕事の付加価値を結び付けてモチベーションアップにつなげていく、という新しい活動を西松とやり始めています。

CPPの導入を検討されている方、これから試験を受けようとされている方に応援のメッセージをいただけますでしょうか?
繁田
個人的には、教科書的なところも大事だと思いますが、やはり実態とどのように結びついているのかが大事だと思っています。弊社は工場を所有しておらず、また最近はコロナの影響で現場に行くこともできていませんが、現地にいって現物をみて、現実に起きていることと、CPPに書かれている内容がどのように結びついているかっていうところが分かってくると、自分の力になってくると思います。
勉強も大事ですが、三現主義(現場・現物・現実)で、知識を結びつけることが受験に合格するという観点では近道なのではないかと思っています。
西松
例えば購買のやり方で困っている方、疑問を持っている方、腹落ちしていない方に対しては教科書的な位置づけだと思いますので、学んだものを実践してみると非常に利用価値が高いのではないかな、と思います。
あとは、人材育成は恐らくどこの会社でも必要と思いますが、教育担当者にとっても参考になり、客観性を身につけることができると思います。
私は、12年程購買業務に携わっていますが、後進への教育の際に、自分の経験だけでは補い切れなかった部分や説明に自信が持てなかったところもCPPから自信を持つこともできました。
決して、取り組んで損はないかと思います。
原口
私が言うのもなんですが、私は購買にきて10年ちょっとで、その前は開発を経験していたのですが、異動してきた当時は、正直、購買部門は高齢化が進んでいました。
その中で色々な実務経験をさせてもらったのですが、教育指導はほとんどなく、先ほどあった”言い伝え”や”一子相伝”のようなやり方が続いていました。
それでも実務を覚えながら、何とかこなしていたのですが、キホンのキが無い中、先輩方が「やっぱり若手教育していかなくてはいけない」「若い方をどんどん採用していかないといけない」という考えに変わってきたことに加えて、ソーシングをしている、お取引様から部品を供給していただいているので購買部門がしっかりしていかないと安定供給の観点から危機感みたいなこともありました。
そこからメンバーが頑張って、色々試行錯誤して、若い社員方も増えていって、CPPを活用しながら、今では若いメンバーも凄く積極的にやっていただいて非常に助かっていますし、良い材料、良い人財、いい雰囲気なのかなと思っています。