2024年3月12日
日立ビルシステムでは、調達部門における戦略人財育成の一環としてCPP資格を導入した。調達の体系的理解やスキル強化を目的に、複数名による取得や勉強会の開催、A級取得者の誕生など、実務と結びついた活用が進んでいる。非製造業ならではの視点から、CPPがもたらす価値をお伺いました。
調達本部 調達企画部 調達企画グループ 部長代理 飯森 直洋 様 主任 丸川 貴志 様 主任 成田 拓 様
調達本部 調達二部 購買グループ 主任 熊谷 紗也子 様
※以降敬称略、所属・役職は2023年11月16日時点

御社における調達部門の位置づけと、CPP導入以前の課題について教えてください。
飯森
日立ビルシステムは、昇降機やビル設備を中心に、設計・施工・保守・管理までを一貫して手がけるビルソリューション企業です。調達企画部では、資材調達の戦略立案から教育、コストマネジメントまでを横断的に担当しており、私はその中で人財育成と教育体系の設計を主に担っています。
従来はOJTを中心とした教育に頼っていたため、調達人財の力量を客観的に評価し、体系的に育成する仕組みが不足していました。加えて、非製造業特有の「多様で間接的な購買」が多い当社では、調達業務の幅が広く、知識の標準化と継承が課題となっていました。

CPP導入のきっかけと、どのように社内で展開していったのかを教えてください。
飯森
CPPの存在を知ったのは、調達人財の能力を可視化し、体系的な学びを提供したいという課題からでした。教材を確認すると、理論と実務の両面をバランスよく網羅しており、調達の幅広い業務を体系立てて学べる優れた内容だと感じました。まずは調達企画部内で数名が先行して受験し、試験の難易度や必要な学習時間を確認。その後、希望者を募って徐々に対象範囲を拡大し、全社的な取り組みへとつなげました。
導入初期には、業務時間内での学習確保や受験に対する不安の声もありましたが、勉強会の開催や過去問題の共有といった支援体制を整備することで、徐々に安心感が醸成されました。特に受験者同士で問題を出し合い、理解を深め合う形式が効果的で、自律的な学びの風土が形成されていったと感じます。こうした取り組みの成果として、複数名のB級取得に加えてA級合格者も誕生し、社内でのCPPの認知と信頼が一層高まりました。
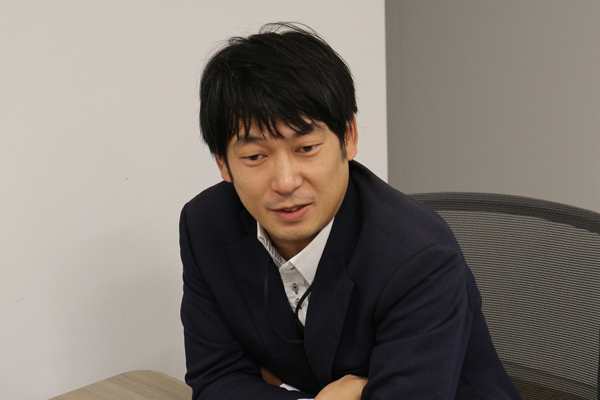
CPP取得が、実務にどのように生きているのか教えてください。
丸川 環境や人権といったESG視点での調達方針の策定・実行を担当しています。各部門や取引先との調整が必要で、共通言語と論理的な整理力が不可欠ですが、CPPを通して得た知識により、調達領域における専門用語や管理手法の理解が深まり、社内外での説明や交渉が格段にスムーズになりました。自分の担当領域だけでなく、調達全体の流れの中でどう位置付けられるかを把握できるようになった点も大きいです。
熊谷 私は、昇降機設置後の保全部品や間接材を扱っており、社内外のステークホルダーとの調整が多く、数量や納期だけでなくコスト管理や仕様確認など、広範なスキルが求められます。CPPを学んだことで、調達業務の基礎理論を再確認でき、現場判断の際にも裏付けを持って意思決定ができるようになりました。提案やレポートにも説得力が増し、社内評価にもつながっています。

製造業ではない貴社でも、CPPが有効に機能している理由は何でしょうか?
成田 私は教育体系の設計と社内研修の実施を担当しています。当社の調達業務は施工や保守サービスに関わるため、一般的な製造業とは異なる特性を持ちますが、それでもCPPの知識体系は非常にフィットしています。全体像を把握したうえで、業務に合わせた応用力を育てることができるからです。実際に社内の教育研修にもCPPの内容を取り入れており、受講者の理解度が上がったことを実感しています。
飯森 ビル設備やサービスは、多様で変動的な調達が求められます。だからこそ、CPPが提供する原則や考え方は、私たちの実務に応用しやすいと感じています。単なる知識取得にとどまらず、組織内での共通認識の醸成や、教育制度のベースとしても非常に有効です。

CPPがご自身の成長やキャリアに与えた影響を教えてください。
成田 私は部門教育の責任者として、まず自らCPPを受験し、B級・A級ともに取得しました。特にA級は実務の応用力が問われるため、日々の業務において自分が何を重視し、どのように判断しているかを見つめ直す良い機会になったと実感しています。現在は、勉強会や教材選定にも携わっており、学習支援体制の構築にもCPPの経験を活かしています。
丸川 CPPを通じて、自分の得意・不得意が可視化されました。特に不得意な領域を自覚できたことで、今後のスキル開発の方向性が明確になりました。若手・中堅・ベテランと、それぞれの段階に応じた学びがある点でも、長期的な人財育成に適した資格だと感じています。
熊谷 業務に慣れてきたタイミングでCPPを学び、視野が大きく広がりました。日々の業務に追われていても、自分の仕事が調達全体のどこに位置するのかを理解できるようになったことは大きな収穫です。もし初級編のようなステップアップ制度が整えば、後輩たちにも積極的に勧めたいと思っています。