2024年6月11日
三菱UFJ銀行の「購買戦略室」は、間接材購買の専門部門として2020年に新設された。銀行という非製造業の中で購買業務の標準化と効率化に取り組むこの部署では、CPP資格を活かした実践が進んでいる。今回は、CPPを取得した齊藤隆氏に、実務への影響と自身の成長についてお伺いしました。
経営企画部 購買戦略室 購買・調達グループ 次長 齊藤 隆 様
※以降敬称略、所属・役職は2023年12月20日時点
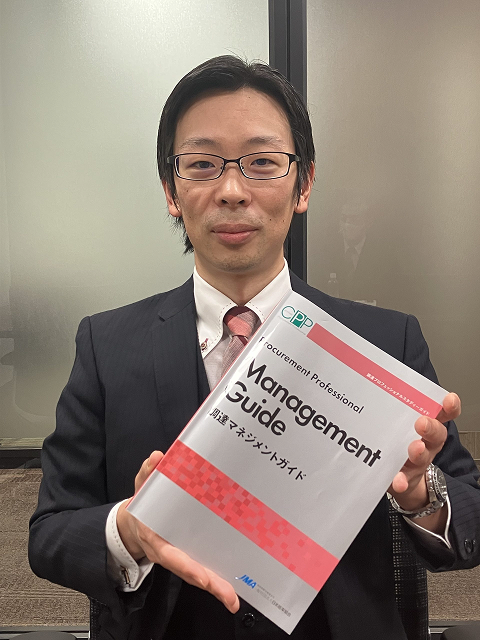
2020年に購買戦略室が設立されましたが、その背景や目的について詳しくお聞かせください。
齊藤
購買戦略室が立ち上がった背景には、経費の最適化を通じて企業体質を強化するという、非常に現実的かつ経営的な課題がありました。金融機関では、収益源が利ざやや手数料収入に限られ、業績の改善には限界があります。そこで「コスト構造の見直し」、特に、全社的な間接材の管理が急務となったのです。
2020年という設立のタイミングも重要です。外部環境が大きく変化し、収益構造だけでなく支出構造の見直しも求められる中で、支出をコントロールする力がより一層重要視されるようになっていました。そうした課題に真正面から取り組むため、組織横断型の専門部門として購買戦略室が新設されたのです。
CPP資格を取得しようと思われたきっかけと、学び始めて感じたことを教えてください。
齊藤
取引先の方との会話の中で「CPPは購買業務を体系的に学べる良い資格ですよ」と教えていただいたのがきっかけでした。当時の私は、経験則で購買業務を進めることが多く、「果たしてこれで良いのか」という漠然とした不安も抱えていたんです。
調べてみると、CPPは購買の基本から応用、コンプライアンス、戦略的調達まで非常に幅広い知識をカバーしており、これまでの経験とつなげられる要素が多かったんですね。学んでみると、だからこの業務はこうすべきだったのかと、今まで感覚でやっていたことに理論的な裏付けが得られる感覚がありました。
また、非製造業でも活かせる内容が多く、現場に使えると確信して取得を決意しました。勉強は大変でしたが、得られたものは非常に大きかったです。
CPPを取得したことで、実務や組織の中にどのような変化が生まれましたか?
齊藤
大きな変化は、プロセスの見える化です。それまでは、各部門がバラバラに購買を行っており、判断基準や調達ルールが曖昧な状態でした。CPPで学んだ購買の基本原則に基づき、業務フローや評価基準、稟議プロセスを整理・統一することで、属人化を防ぎ、組織全体での効率化と透明性の向上を実現できました。
また、CPPで得た知識をもとに資料を作成したり、社内説明を行うときの説得力が大きく変わりました。数値や評価項目に基づいたロジカルな説明ができるようになり、関係部署との調整もスムーズになったと実感しています。結果的に、業務改善のスピードが上がっただけでなく、購買という業務の価値を社内に認識してもらえるようになったと思います。
CPPは製造業向けという印象もありますが、金融業での活用にはどのような可能性を感じましたか?
齊藤
おっしゃるとおり、CPPの元々の設計は製造業を想定したものかもしれません。でも、だからこそ非製造業に導入すると型が整うのです。たとえば金融業では、「何を、どこから、どういう基準で買っているのか」が明確でないケースが多く、同じカテゴリーの商品でも価格差や品質差が大きくなりがちです。
CPPを学ぶと、サプライヤー評価の軸や契約管理の観点、さらにはCSRやリスク管理まで幅広く考えられるようになります。それを活かし、行内では評価シートを新たに導入し、調達先の妥当性を可視化しました。これにより、結果だけでなく、判断のプロセスにも信頼が集まるようになりました。業種に関係なく原則を持つことの大切さを強く感じました。
CPP取得がご自身のキャリアや意識に与えた影響を教えてください。
齊藤 CPPの学びを通じて、自分の仕事に対する視野が一段と広がりました。それまでは、目の前の業務をどう処理するかに集中しがちでしたが、「なぜこのプロセスが必要なのか」「どの判断が組織にとってベストなのか」と、より上位の視点で物事を捉えるようになりました。 また、過去の自分の判断や対応をCPPの理論で振り返ってみると、「ここは正しかった」「ここは改善できた」と自己評価が冷静にできるようになりました。それが自信にもつながっています。年齢を重ねた今だからこそ、実務経験と資格学習の相乗効果を実感しています。 さらに、若手への教育にも活かしています。OJTだけでは伝わらない考え方や背景を、CPPの内容をベースに体系立てて共有することで、部門全体のスキルアップにも貢献できていると感じます。